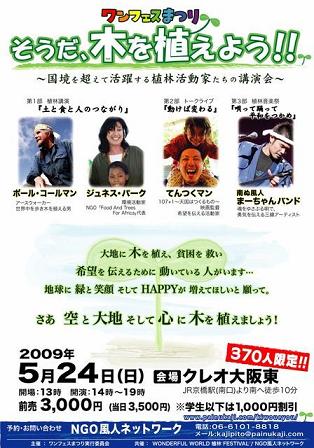4月28日雨。これから先バイオディーゼル燃料を作るのにかかせない水酸化カリウムを入手したので、1回の反応に必要な量に仕分け作業をすることにした。バイオディーゼル燃料を自分で走りながら作るという事は、普段目には見えない仕込みや準備にとても時間がかかるものだ。
カリウムやメタノールの取り扱いは十分注意が必要なので、安全な場所でマスクやゴーグルを着用はかかせない。海外でのこの作業は、悪条件が多く、炎天下の外でやることが多かったので、けっこう大変だった。
海外で入手した水酸化カリウムは、場所によって種類や色も異なり、右下の写真は緑色のものがロシアで手に入れたもの。白い色は日本で手に入れたものだ。緑色のカリウムは、メタノールと溶け具合が悪く、日本に帰って来てから何度もパイプを詰まらせるという事態を招いた。以前はプラスチックのケースに入れていたが、いろいろアドバイスをいただいている加藤商店さんの助言でリード製のジップロックを使用するようになった。これだと場所をとらず収納に便利なのだ。